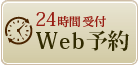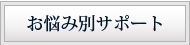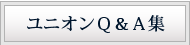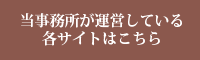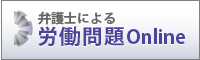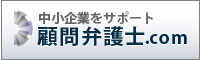ユニオンから労働委員会への救済申立てに期限はありますか?


労働組合による申立ては、不当労働行為があったとされる日から1年以内に行わなければならず、1年を過ぎた申立ては却下となります。
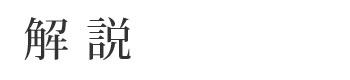
申立期限
 労働者や労働組合による不当労働行為に対する労働委員会への救済申立ては、行為の日から1年以内に行わなければなりません(労組法27条2項)。
労働者や労働組合による不当労働行為に対する労働委員会への救済申立ては、行為の日から1年以内に行わなければなりません(労組法27条2項)。
なお、「継続する行為については、その終了する日」と規定されています。
この期限を定めた趣旨は、行為から一定期間を経過すれば証拠の収集や事実関係の把握が難しくなることや、救済の実益がなくなることなどが挙げられます。
継続する行為の考え方
 ここで問題となるのが、「継続する行為」とはどのような行為を指しているのかということです。
ここで問題となるのが、「継続する行為」とはどのような行為を指しているのかということです。
例えば、解雇については、会社がその意思表示をすることで行為としては完了し、解雇の効力発生日から1年間が申立期限となります。
しかし、組合員に対する人事考課の低査定に基づく、昇給や賞与の差別事案において、こうした行為が「継続する行為」と評価することができるかが裁判で争われてきました。
【参考裁判例】紅屋商事事件 最三小判平3年6月4日(民集45巻5号984頁)
 この裁判例では、使用者側が自ら行った昇給査定と賃金支給行為はそれぞれ別個の行為であり、昇給査定を行ってからすでに1年を経過していることから救済申立ては不適法であると主張していた。こうした使用者側の主張に対して、最高裁判所は以下のように判旨している。
この裁判例では、使用者側が自ら行った昇給査定と賃金支給行為はそれぞれ別個の行為であり、昇給査定を行ってからすでに1年を経過していることから救済申立ては不適法であると主張していた。こうした使用者側の主張に対して、最高裁判所は以下のように判旨している。
「上告人(使用者)が毎年行っている昇給に関する考課査定は、その従業員の向後一年間における毎月の賃金額の基準となる評定値を定めるものであるところ、右のような考課査定において使用者が労働組合の組合員について組合員であることを理由として他の従業員より低く査定した場合、その賃金上の差別的取扱いの意図は、賃金の支払いによって具体的に実現されるのであって、右査定とこれに基づく毎月の賃金の支払いとは一個の不当労働行為をなすものとみるべきである。そうすると、右査定に基づく賃金が支払われている限り不当労働行為は継続することになるから、右査定に基づく賃金上の差別的取扱いの是正を求める救済申立てが右査定に基づく賃金の最後の支払の時から一年以内にされたときは、右救済の申立ては、労働組合法二七条二項の定める期間内にされたものとして適法というべきである。」(括弧書き、下線部執筆者加筆)
 この裁判例からすると、昇給差別に関しては、次の昇給査定が行われるまでは「継続する行為」として救済申立てが可能であるといえます。
この裁判例からすると、昇給差別に関しては、次の昇給査定が行われるまでは「継続する行為」として救済申立てが可能であるといえます。
その後の裁判例でも同様に考えられています(住友重機械工業事件(東京地判平20年11月13日労判974号5頁))。
なお、使用者が差別的な昇給査定を繰り返すことによって数度の昇給査定を原因とする賃金格差が生じている場合に、複数回の昇給査定の全体を一体のものとして、「継続する行為」といえるかについては争いがあります。
この点について、当該行為はまさに一つの目的のためになされる一体の行為と解されるので、原則として「継続する行為」と解すべきであるという見解も学説上はあります(西谷214頁)。
しかしながら、裁判例では、上述のとおり、次の昇給査定が行われた場合は前の査定とは別個の行為として取り扱っています。
 もっとも、裁判例はその判断を前提にしつつも、蓄積された賃金格差全体を将来に向かって解決する労働委員会の救済命令については、裁量の逸脱はないとして容認しており(千代田化工建設事件(東京地判平9年7月23日労判721号16頁)、肯定説と否定説の間の中間説を採用していると評されています(菅野1056頁)。
もっとも、裁判例はその判断を前提にしつつも、蓄積された賃金格差全体を将来に向かって解決する労働委員会の救済命令については、裁量の逸脱はないとして容認しており(千代田化工建設事件(東京地判平9年7月23日労判721号16頁)、肯定説と否定説の間の中間説を採用していると評されています(菅野1056頁)。
昇給差別と異なり、就業時間中に継続的に組合バッジを着用する労働組合員に対し、毎年繰り返される懲戒処分について、裁判所は組合バッジの着用やその取り外し指示に従わないという組合員の行動は、社会的事実としては勤務日ごとに1個の行為であり、それぞれの懲戒処分はその日ごとの行為に対して行われた、異なる処分であるという理由で、一貫した不当労働行為の意思のもとに行われた継続する行為と主張していた労働組合の主張を斥けています(東日本旅客鉄道事件(東京高判平25年11月28日別冊中労時1455号38頁))。
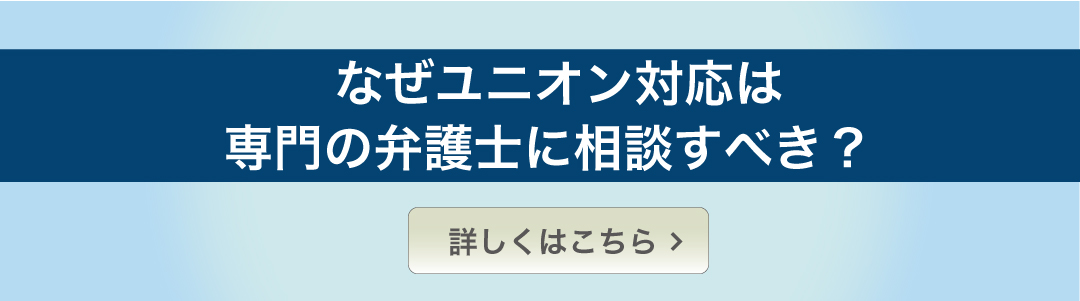
その他の関連Q&A
-
1
労働組合(ユニオン)とは? -
2
不当労働行為とは? -
3
労働委員会の手続等 -
4
組合活動の妥当性 -
5
団体交渉への対応方法 -
6
労働協約とは? -
7
争議行為への対応 -
8
紛争の解決制度