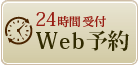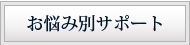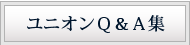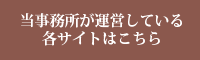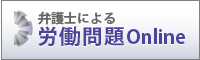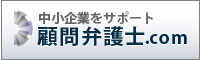パートタイマーのような非組合員についての団体交渉も応じる必要はありますか?
 労働組合(ユニオン)が組合員以外のパートタイム従業員の労働条件についても団体交渉を求めています。
労働組合(ユニオン)が組合員以外のパートタイム従業員の労働条件についても団体交渉を求めています。
このような場合でも団体交渉に応じなければなりませんか?


非組合員の労働条件であっても、組合員の労働条件に影響を及ぼす場合は団体交渉に応じる必要があります。
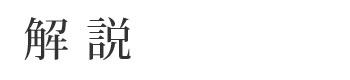
義務的団項事項の定義
 団体交渉でいかなる議題について交渉するかは、基本的には交渉当事者が事由に決めることができ、制限があるわけではありません。
団体交渉でいかなる議題について交渉するかは、基本的には交渉当事者が事由に決めることができ、制限があるわけではありません。
例えば、株主総会の決定事項なども、使用者が任意に応ずるかぎり、団体交渉の議題にあげてかまいません。
しかし、労組法は第7条において、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否すると不当労働行為にあたると規定しています。
そして、使用者の団交応諾義務を具体化するために、この団体交渉拒否に対する行政救済の制度を定めています(労組法27条以下)。
そのため、不当労働行為救済制度との関係で、労働者の要求に対して使用者が交渉を拒否できない対象事項の範囲を把握しておく必要があります。
その使用者が交渉を拒否できない対象事項を義務的交渉事項といいます。それ以外の事項は、任意的交渉事項と呼ばれます。
義務的交渉事項の一応の定義としては、「組合員である労働者の労働条件やその他の待遇や当該団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なもの」と表現されます(菅野655頁)。
例えば、賃金、労働時間、休息(休憩・休日・休暇)、安全衛生、災害補償、教育訓練などが「労働条件やその他の待遇」の典型です。
また、組合員の配転、懲戒、解雇などの人事の基準(理由ないし要件)や手続(労働組合との協議、組合の同意)も「労働条件やその他の待遇」であり、義務的交渉事項です。
非組合員の労働条件
 前記の義務的団交事項の定義からすれば、労働組合は組合員の労働者の労働条件その他の待遇についての団体交渉権を有し、非組合員のそれらについては団体交渉権を有していません。
前記の義務的団交事項の定義からすれば、労働組合は組合員の労働者の労働条件その他の待遇についての団体交渉権を有し、非組合員のそれらについては団体交渉権を有していません。
したがって、例えば、当該労働組合の組合員でないパートタイム労働者や派遣労働者などの労働条件について、使用者が団体交渉を拒否しても不当労働行為にあたらないように思えます。
しかし、非組合員の労働条件であっても、間接的には組合員の労働条件に重要な影響を及ぼすことがあります。そのような場合、使用者は非組合員の労働条件について、団体交渉応諾義務を負うと解すべきです。
例えば、いまだ労働組合に加入していない新規採用社の初任給の問題については、組合員の勤続による賃金カーブのベースになることから組合員の賃金問題に重要な影響を及ぼします。したがって、原則として義務的団交事項にあたります。
 この問題について、裁判所(根岸病院事件)は、
この問題について、裁判所(根岸病院事件)は、
「非組合員である労働者の労働条件に関する問題は、当然には上記団交事項にあたるものではないが、それが将来にわたり組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関わりが強い事項については、これを団交事項に該当しないとするのでは、組合の団体交渉力を否定する結果となるから、これも上記団交事項にあたると解すべきである。」
という判断基準を示したうえで、
 「一審原告病院においては、一審原告組合が、春闘において賃金体系の確立及びそれに次ぐものとして初任給の明示・年齢ポイント賃金の設定等を毎年要求として掲げ、初任給については、昭和60年以降平成7年まで、当年度の初任給は前年度の初任給に当年度のベースアップ分等を上乗せした金額とされ、昭和63年を除き、一審原告病院は夏季一時金要求に対する回答書の添付資料として同年度の初任給表(職種別の初任給額の一覧表)を一審原告組合に示し、平成8年から平成10年までは、初任給額が平成7年度の金額に固定され、上記の扱いはされなかったものの、一審原告組合へ初任給凍結の通告がされ、その後においても翌年度の春闘要求書に対する回答書に初任給額を記載し、一審原告組合に対し明らかにされていたものである。
「一審原告病院においては、一審原告組合が、春闘において賃金体系の確立及びそれに次ぐものとして初任給の明示・年齢ポイント賃金の設定等を毎年要求として掲げ、初任給については、昭和60年以降平成7年まで、当年度の初任給は前年度の初任給に当年度のベースアップ分等を上乗せした金額とされ、昭和63年を除き、一審原告病院は夏季一時金要求に対する回答書の添付資料として同年度の初任給表(職種別の初任給額の一覧表)を一審原告組合に示し、平成8年から平成10年までは、初任給額が平成7年度の金額に固定され、上記の扱いはされなかったものの、一審原告組合へ初任給凍結の通告がされ、その後においても翌年度の春闘要求書に対する回答書に初任給額を記載し、一審原告組合に対し明らかにされていたものである。
そして、一審原告組合がこのような初任給額の決定に異議がなかったことから、その額をめぐり労使交渉がされることはなかったが、一審原告組合が賃金体系の確立を求め、常勤職員の賃金のベースとなる初任給額に重大な関心を寄せ、このことは一審原告病院においても認識し、上記のような措置を取っていたことが明らかである。
そして、一審原告病院においては、常勤職員の新規採用年度以降の基本給は、初任給額に翌年度以降の春闘で一審原告組合と妥結した本給の定期昇給分、ベースアップ分及び第二本給増額分を加算することにより決定されており、初任給額がその後の賃金のベースとなる。
入職年が異なることで初任給額が異なれば、賃金ベースを異にして上記加算がされるため、初任給額が大幅に減額された年以後に入職した者は低額の賃金をベースに加算されるにすぎないことから、他院での経験年数による加算をしても、通算して同じ経験年数の者でも入職が大幅減額の前か後かによって大幅な賃金格差が生ずるおそれが生ずる。
労働者の間で入職の時期の先後によって賃金ベースが異なり、大幅な賃金格差があることは、実際には人材確保のために調整手当で差が縮小されることがあるとしても、労使間の交渉において、賃金の高い労働者の賃金を抑制する有形無形の影響を及ぼすおそれがあるのみか、労働者相互の間に不満、あつれきが生ずる蓋然性が高く、このことは組合員の団結力に依拠し賃金水準の向上を目指す労働組合にとって看過しがたい重大な問題というべきである。
そして、本件初任給引下げは、上記のような一審原告病院における賃金決定の仕組みから考えると、在職中の組合員を抑制する有形無形の影響を及ぼす事項であり、本件初任給引下げが適用された平成11年当時は、新規採用者の少なからぬ者が短期間のうちに一審原告組合に加入していたと認められるから、本件初任給引下げは短期間のうちに組合員相互の労働条件に大きな格差を生じさせる要因でもあるから労使交渉の対象となることが明らかである。
そうすると、初任給額の問題は、直接的には一審原告組合の組合員の労働条件とはいえず、これまで一審原告病院において初任給が引き下げられたことがないことから、労使交渉の対象とされたことがなく、一審原告病院は経営事項として労使交渉の対象外の事項と考えていたものではあるが、初任給額が常勤職員の賃金のベースとなることから、一審原告組合が初任給額を重視し、一審原告病院においてもこのことを理解し各年度の初任給額を一審原告組合に明らかにするとの運用がされてきたものであり、本件初任給引下げは、初任給の大幅な減額で、しかも、一審原告組合の組合員間に賃金格差を生じさせるおそれがあるものというべきであり、将来にわたり組合員の労働条件、権利等に影響を及ぼす可能性が大きく、組合員の労働条件との関わりが極めて強い事項であることが明らかである。
したがって、本件初任給引下げは義務的な団交事項に当たるものと認められる。」
と判示しました(東京高判平19.7.31労判946号58頁)。
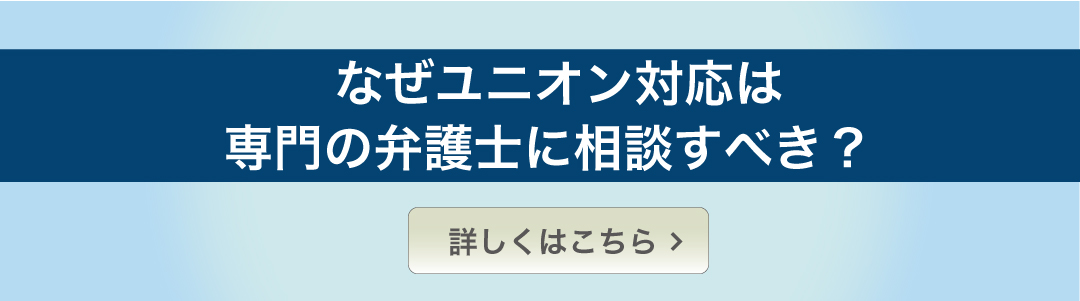
その他の関連Q&A
-
1
労働組合(ユニオン)とは? -
2
不当労働行為とは? -
3
労働委員会の手続等 -
4
組合活動の妥当性 -
5
団体交渉への対応方法 -
6
労働協約とは? -
7
争議行為への対応 -
8
紛争の解決制度